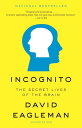脳には自ら変化し続ける「可塑性」という性質があります。アメリカの著名な脳科学者であるデイヴィッド・イーグルマンは、脳は可塑性があるというより、変化そのもので、経験に基づいて変わり続けると言います。私たちは生まれたときに与えられたDNAの虜ではなく、生涯を通じて変化し続け、決して終点に達することはありません。
~ ~ ~ ~ ~
人生を形作るのは遺伝子ではなく経験
私たちは、自分より秀でている人たちを見て「DNAが違うから敵わない」とか「そもそも遺伝子で勝負がついている」などと表現したりしますね。
多くの人が、遺伝子によって、自分の知性や身体能力の多くが決まると信じています。しかし、実際には、遺伝子は私たちに脳の基本設計図や初期プログラム、身体の特性を提供するだけです。
遺伝子がさまざまな異なる可能性を人に与えるのは確かです。しかし、私たちは完全にプログラムされて生まれてくるわけではありません。生まれた後の経験や環境との相互作用の方が、私たちがどのような人間になるか、どこまで成長するか、人格や能力を形成するにあたって、はるかに大きな役割を果たします。
偉大なアスリート、研究者、成功した起業家として生まれてくる子はいません。もし遺伝子がすべてを決定するのならば、私たちの脳は生まれたときから何も変わりません。
脳は経験に基づいて自らを常に再配線していきます。脳は脳を書き換え続けます。どんな子供でも、繰り返しの経験、トレーニング、粘り強く努力することによって自らを変え、優れたスキルを身に付けることができます。
私たち人間は、他の多くの動物と異なり、この世に生まれ出た段階ではほとんど出来上がっていません。
他の動物の中には、生まれてから早い段階で、親の支援なく生きていけるようになる動物がたくさんいます。しかし、人間は何年にも渡り、両親や大人たちのサポートなしに生きていくことはできません。周囲の人たちと交わりながら、何年もかけて成長し、社会の中で生きるすべを学び、独り立ちしていきます。
これは人間の弱みであると共に強みでもあります。
なぜなら、この特性によって、人間は環境に応じて自らを適応させることができるからです。どのような環境に生まれ出ても、その環境に自分を合わせることができます。
多くの動物は環境がまったく異なる場所に生まれては、生きていくことができません。生まれ出た段階で多くの機能が固定されていて、違う環境に適応できないからです。
経験に基づいて脳が自らを再配線し、変化、適応、成長する能力を、英語で「Neuroplasticity:ニューロプラスティシティ」や「Brain plasticity」と言います。日本語では「神経可塑性」や「脳の可塑性(かそせい)」と言います。
私たち人間が持つ遺伝子はせいぜい20,000個です。しかし、脳の再配線に直接影響を与えるニューロン(神経細胞)の数は860億で、その接続数は200兆にも及びます。遺伝子は人生のドミノの最初の1ピースに過ぎないのです。
~ ~ ~ ~
今回は、アメリカの著名な脳科学者で、スタンフォード大学で脳科学を教えているデイヴィッド・イーグルマン(David Eagleman, 1971 – )2020年著の「Livewired : The Inside Story of the Ever-Changing Brain(邦題)脳の地図を書き換える:神経科学の冒険」の概要を紹介します。この本は、脳の可塑性、つまり生涯を通じて適応、再配線、変化する脳の驚くべき能力について書いています。
なお、いつもの通り、私は英語版を読んでおり、日本語版との言葉使いや表現の違いについてはご了承ください。
~ ~ ~ ~ ~
脳の可塑性(かそせい:plasiticity)と、変化し続ける脳(ライブワイヤード:livewired)
「Neuroplasticity:脳の可塑性」という用語は、1948年にポーランドの脳科学者イェジィ・コロノスキー(Jerzy Konorski, 1903 – 1973)によって初めて使用されました。彼は、経験に応じて脳の神経接続が変化する様子を説明するためにこの用語を使いました。
ただし、脳の適応性の概念はさらに古くから存在しています。19世紀後半、アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズ(William James, 1842 – 1910)は、「可塑性」という言葉は使用しなかったものの、脳は経験に基づいて変化する可能性があると示唆していました。
実は、今回紹介するデイヴィッド・イーグルマンは「Neuroplasticity:脳の可塑性」という言葉を使うことを好んでいません。なぜなら、この用語は、脳はプラスチックのように柔らかくなった後に違う形に変化して固定するとか、単に柔軟であるというだけの間違った印象を与えかねないからです。
脳は「可塑性がある」というよりも「可塑そのもの」であり、常に変化し続けていて終わりがありません。イーグルマンが「ライブワイヤード:Livewired」という言葉を使っているのは、それを表現するためです。
脳をハードウェアとソフトウェアに分けることはできません。脳は「ライブウェア」なのです。脳は生きているのです。
適応するだけでなく、経験に基づいて常に変化し、自らを書き換え続けているのです。例えば、あなたがここまでの文章を読んだだけでも、脳は既に変化したのです。脳は生涯を通じて再配線し続け、決して終点に達することはありません。
本書を通じてイーグルマンはその考えを裏付けるさまざまな事例を紹介しています。
そのうちのいくつかをここで取り上げましょう。
~ ~ ~ ~ ~
脳は失われた機能を補ったり回復するため再配線する
健常者の脳は、視覚情報は視覚野(visual cortex)、触覚は体性感覚野(somatosensory cortex)、聴覚情報は聴覚野(auditory cortex)といったように、入力された情報を脳の別々の場所で処理します。
では目が見えない人の視覚野は機能しないのかというとそうではありません。
目が見えない人の脳では、触覚や聴覚など他の感覚を処理する領域が視覚野を利用します。その結果、聴覚や触覚などの他の感覚が鋭くなります。同様に聴覚障害者の聴覚野は、視覚と触覚の入力に取って代わられます。
目の見えない人は、ものに触れたり、音を通して「見る」ことができるのです。同様に、例え人が手足を失っても、脳は信号処理を停止するのではなく、その変化に合わせて再編成します。
視覚障害者の中には、自分で音を発してその反響を聞くことで、ものの位置を特定できる人もいます(エコーロケーション)。彼らの脳は視覚野を再利用して、音に基づいて空間認識処理しているのです。
なお、さらに言えば、イーグルマンは、視覚野、体性感覚野、聴覚野といった脳領域も、最初からその場所に存在しているわけではなく、耳や口や目の位置などから、可塑性によって、その脳の範囲がそれらの機能を持つようになったという考えも紹介しています。
障害があっても、芸術などで秀でた能力を発揮する方々も少なからずいますが、これも、障害のある領域の配線がされない一方で、別の脳領域に健常者よりも多く配線されているからです。
脳卒中を生き延びた人は、その後の新しい経験と治療に基づいて脳が再配線されるため、歩くこと、話すこと、書くことを再学習できます。可塑性により、リハビリテーションを通じて失われた能力を回復することができます。
よく事故にあって身体機能を失った患者に対して「絶対に回復しません」という医者がいますが、正しくありません。人間は残された機能を利用して失った機能を補ったり回復する能力を持っており、仮に可能性は少なくてもゼロということはないからです。
これは障害者や重病患者に限りません。
例えば、健常者が数日間目隠しをして視覚情報を遮断して過ごしただけでも、聴覚が鋭くなります。つまり、脳が1つの感覚を別の感覚の役割を果たすように利用するのです。しかし、目隠しを取り外せば、すぐに元の状態に戻ります。
これは、脳が柔軟であるだけでなく、常に役割を再割り当てしていることを証明しています。そして、脳は今まで考えられてきた以上に驚くほど短期間で変わっていくのです。脳神経の再構築は、数日から数時間で行われます。
~ ~ ~ ~ ~
ニューロンは脳領域を奪い合う
以上の説明から、ニューロン(脳の神経細胞)は互いに助け合っているというイメージを持つかもしれません。しかし、実際はその反対です。ニューロンは限られた脳領域で勢力を拡大しようと、互いに競い合い、脳領域を奪い合っています。
記憶の敵は、他の記憶です。
同じことを繰り返しやることで、その脳配線が強化されていきます。一方で、それ以外の使われない配線は弱くなっていきます。
例えば、会計士がキャリアを変えてピアニストになった場合、指に割り当てられた脳領域は拡大し、数字に割り当てられた脳領域は縮小します。
複雑な市街地図を暗記しなければならないロンドンのタクシー運転手は、その長年の経験により、海馬(脳のナビゲーションセンター)が大きく発達します。
新しいスキル(バイオリンの演奏など)を習得すると、まったく新しい神経回路が形成されます。新しい言語を学ぶと、脳の言語関連領域の灰白質がより高密度になります。
数学やスポーツが苦手、あるいは創造性がないのは遺伝のせいだとよく言われますが、それには、あることを継続的な努力によって向上させることで、その他の機能が低下することも関係しています。
~ ~ ~ ~ ~
脳はなぜ夢を見るのか?
私たちはなぜ夢を見るのでしょうか?
本書によれば、夢を見ることで、寝ている間に視覚情報を処理する視後頭葉皮質をアクティブに保つためです。
寝ている間、私たちは目を閉じています。しかし、ニューロンは脳領域を奪い合うため、寝ている間の短い時間でさえ、何もしなければ、視後頭葉皮質が、隣接する他の領域に奪われていくのです。
睡眠は、触覚、聴覚、味覚、嗅覚には何の影響も与えません。暗闇では視覚だけが損なわれます。
レム睡眠中に、私たちは、夢を視覚的に体験します。私たちが夢を映像としてはっきり覚えていることがあるのは、このためです。
夢を見ることで視覚機能を規則的に活性化しておかないと視覚領域が他の脳機能に侵食されてしまうのです。
では、生まれつき目の見えない人はどのような夢を見るのでしょうか?
そのような人たちは夢を「見る」のではありません。視覚体験ではなく、部屋の中を手探りで歩き回ったり、見知らぬ動物の鳴き声を「聞く」といった他の感覚に置き換わった夢体験をするのです。
~ ~ ~ ~ ~
脳は新しいタイプの入力情報を処理でき、付け加えられた機能を利用することができる
イーグルマンの研究は、脳がまったく新しいタイプの入力から情報を得て処理できることを示しています。人工内耳や網膜インプラント、その他、脳に直接信号を送る人工センサーなどです。
私たちは、さまざまな入力周辺機器をいじくり回すことができます。イーグルマンは「ポテトヘッドモデル(Potato head model)」という言葉を使ってそれを分かりやすく表現しています。
つまり、ジャガイモにさまざまなものを突き刺せるように、人間にも新しい機能を外部から付け加えることで、脳はそれをあたかも自分自身の体の一部であるかのように新しい感覚を使いこなせるようになるのです。
例えば、ブレインポートなどのデバイスにより、視覚信号を舌の上で電気信号に変換することで、視覚障害者は舌を通じて「見る」ことができるようになります。
人が上下逆さまの視覚ゴーグルを着用する実験では、脳は最終的にその上下反対の世界に適応し、視覚を正常に戻します。
情報の入力側だけでなく、出力側も同様です。科学者は脳をさまざまな外部デバイスに直接接続する技術を開発しています。ロボットでさえ、最終的には手足の一部として感じられるようになり、脳がまったく新しい身体構造を組み込むことができることを示しています。
実は、人間は既に以前から当たり前のように、そのような外部の道具を自分の体の一部かのようにすでに取り入れて使いこなしています。例えば、包丁やほうき、キーボード、自転車や自動車、義肢、その他のさまざまな道具、VR(バーチャルリアリティ)もある意味その延長に過ぎないのです。
最終的に道具や機械を使用しているという感覚がなくなり、代わりにそれらが身体の自然な一部になっていきます。
図:脳は新しいタイプの入力情報を処理でき、付け加えられた機能を利用することができる
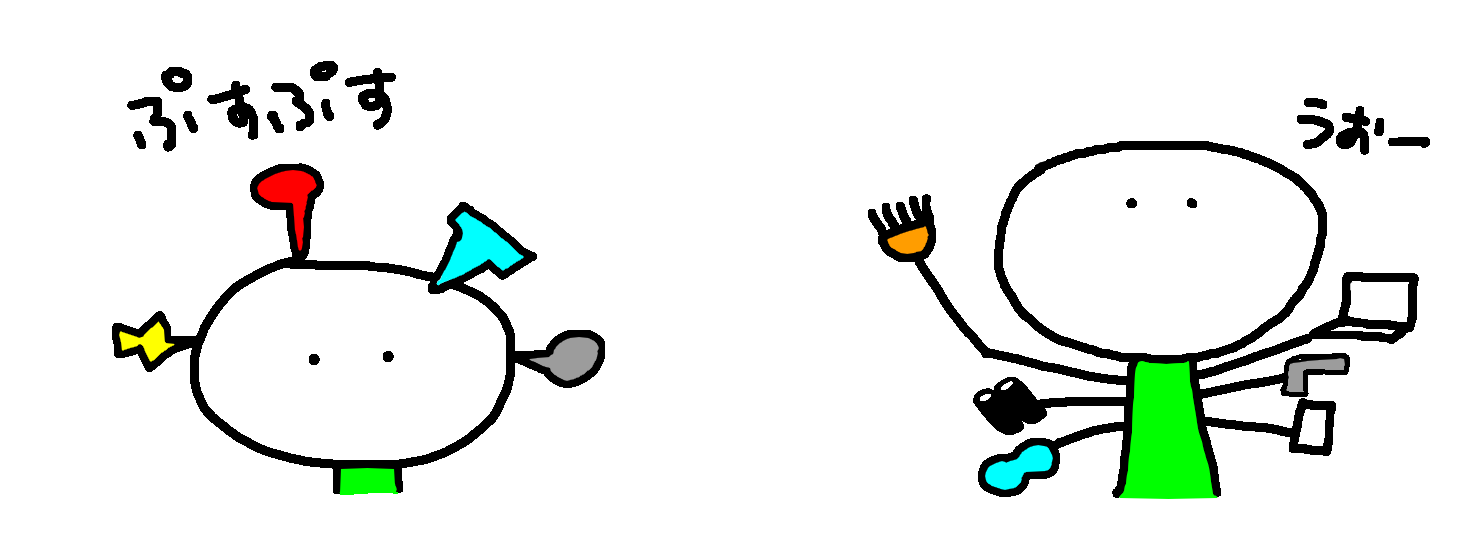
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
以上、デイヴィッド・イーグルマン著の「Livewired(邦題)脳の地図を書き換える」のごく一部を紹介しました。イーグルマンが主張するライブワイヤリングの概念のさわりだけでもご理解いただけたでしょうか?
脳の可塑性やライブワイヤリングは、生まれ持った特性よりも、学習、努力、環境がはるかに重要であることを示しています。脳は決められた時に決められた動作を取るようにプログラムされるだけでなく、その時々の環境を考慮して最適な動作を取るように設計されていきます。
多くの特性(知性、性格、健康など)は、遺伝子よりもライフスタイル、教育、経験によって形成されます。脳は経験に基づいて自らを再構築し続けるからです。
遺伝子は舞台を設定するかもしれませんが、経験があなたの人生の脚本を書きます。
例えば、養子縁組された子供は、実の親ではなく養父母に知性や習慣が似ることが多いのも、育ちや経験が DNAよりも重要であることを証明しています。
私たちの概日時計が24時間に設定されるのも、生まれつきではなく、生まれてから太陽の周期に合わせて自らを調整するからです。暗闇に住む人たちはこの概日時計を持ち合わせません。
逆に言うと、適切な環境や入力がなければ、私たちは健全には発達できません。適切な人との触れ合いがなければ、社会性は身に付きません。
マイケル・ジョーダンは遺伝的に最も才能のあるバスケットボール選手ではありませんでしたが、彼の絶え間ない練習と考え方が彼を最高の選手にしました。
アインシュタインの子供の頃の先生は、彼を鈍いと思っていましたが、彼の好奇心と粘り強さが世界を変える人物にまで成長させました。
ヘレン・ケラーは、耳が聞こえず目が見えないにもかかわらず、教育と決意で読み書きを学び、何百万人もの人々にインスピレーションを与えました。
脳の可塑性は幼少期(2~5才)にピークを迎えますが、高齢になっても、人は新しいスキル、スポーツ、言葉、楽器などを学ぶことで、神経接続が強化され、再編成されます。経験や学習が生涯にわたって成長の源であることを証明しています。
一方で、ライブワイヤリングの原則を利用すれば、私たちは今まで想像もできなかったさまざまな機能を自分たちに付け加えることができますが、個人的には、それは素晴らしいと同時に、恐ろしいとも感じます。
~ ~ ~ ~ ~
さいごに、私はデイヴィッド・イーグルマンが書いた他の書籍も読んでいますが、今回紹介した書籍のみならず、少なくても私が読んだ彼の本はどれも分かりやすく書かれていて、とても読みやすく、理解しやすいです。
特におすすめは、下記の2011年著の「Incognito : The Secret Lives of the Brain:(邦題)あなたの知らない脳」です。この本はベストセラーとなり、当時アマゾンなどで年間最優秀書籍(a Best Book of the Year)にも選ばれました。
脳科学関係の書籍の中には、一般人には理解しずらい本も少なからずありますが、この本は今回紹介した本と同様に、脳科学にまったく不案内な方でも読め、かつ内容の濃い本だと思います。お手に取ってみてはいかがでしょうか?