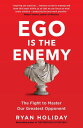エゴとは、自分自身への過度な評価、自信過剰、傲慢、他人を見下す自己中心的な思考と態度です。エゴは私たちの成長を阻害し、あらゆる人間関係の問題の根源となります。健全な社会の形成を妨げ、多くの社会問題を引き起こします。今回は、エゴに溺れた人と、エゴに打ち勝った人をそれぞれ紹介します。
~ ~ ~ ~ ~
はじめに
私たちの人生そして社会の最大の敵は「エゴ」であると、このサイトの記事で繰り返し書いてきました。
そして、これからも引き続き、繰り返し繰り返し書いていきます(笑)。
どこにいようとも、何をしていようとも、私たちの最大の敵であるエゴは、私たち自身の中にいるからです。
それは私自身にも当てはまります。そのため、自分への戒めもかねて、折に触れてエゴについて書いていくのです。
今回紹介するのは、以前にも少し紹介したアメリカの作家であり、メディア戦略家のライアン・ホリデイ(Ryan Holiday, 1987 -)が書いた2016年発刊のベストセラー「Ego Is the Enemy(邦題)エゴを抑える技術」です。
エゴとは、自分自身への過度な評価、自信過剰、傲慢、他人を見下す自己中心的な思考と態度です。
エゴはあらゆる人間関係の問題の根源であり、多くの社会問題の根本原因です。この本は、いかにエゴが私たちの成長を阻害し、健全な社会の形成を妨げるかを紹介しており、章ごとに、エゴに溺れた人たちと、エゴに打ち勝った人たちを取り上げています。
今回は、エゴに溺れた人物の例と、エゴに打ち勝った人物の例を1人ずつ紹介しましょう。
なお、本書も私は英語版を読んでいますので、日本語版との言葉遣い等の違いにつきましてはご了承ください。
~ ~ ~ ~ ~
エゴに溺れ、自らを崩壊した事例
まず、エゴに溺れた人物の事例を紹介しましょう。
1930年代後半、若く有望な劇団主宰者であり、ラジオ番組の名優であったオーソン・ウェルズ(Orson Welles, 1915 – 1985)は、経営難に陥っていた映画製作・配給会社のRKOから、会社を救う策として、2本の映画を脚本し、監督し、自ら演じるという破格のオファーを受けます。
1本目の映画で彼は、ミステリアスな新聞記者が、彼独自の世界観の虜となっていく姿を描くことにしました。
しかし、この映画の製作のことを知った当時の新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハースト(William Randolph Hearst, 1863 – 1951)は、この映画は自分のことを描いたもので、自分に対する攻撃だと思い込みます。実際は、ウェルズはハーストを意図して映画を作成したのではなく、歴史上の様々な人物を総合してイメージを作り上げて設定した書いたのにです。
ハーストは、この映画の上映を妨害するためのありとあらゆる手段を講じます。まず、映画を事前に見せることを要求しました。次に、新聞記者たちに、RKOが配給する一切の映画に関する記事を書かないように圧力をかけました。映画評論家たちには、この映画を酷評するように圧力をかけました。
ハースト系の新聞は全面攻撃をかけ、ウェルズを中傷します。RKOの取締役1人1人にも圧力をかけます。さらには、映画業界全体にも圧力をかけます。ハーストの報復を恐れて上映を拒否する映画館も続出し、興行的には大失敗します。また、ウェルズの2作目はずたずたにカットされ、不本意な形で公開されることになりました。ハーストの攻撃は何年にも続いたため、ウェルズの才能が社会に正しく評価されるまで何十年もかかりました。
ハーストは世界的にも有数の富豪でした。なぜ、若手監督のデビュー作であるフィクション映画をこれほどまでに妨害したのでしょうか?
ウェルズの映画が彼の膨れ上がったエゴを逆なでしたからです。
しかし、皮肉にも、映画を妨害することで、ハーストは彼が望んだ結果とは正反対の結果を呼び込みました。自らの了見の狭さとエゴと醜さを社会に露呈し、築き上げたレガシーを損ない、彼は評判を落としたのです。
そんな不遇なウェルズですが、ある時、ハーストとばったりエレベーターで出会わしたことがあります。その時、彼はどうしたでしょうか?
何と、ウェルズはハーストを食事に招待したのです。ハーストはもちろんその招待を断りました。
ウェルズは、ハーストに自分の人生を台無しにさせませんでした。彼は決してハーストのようにはなりませんでした。彼は幸せな人生を送る選択をしました。結果的に、個人的に幸せになるだけでなく、社会的な名声を得たのも、それを望んだハーストの方ではなく、それに特に執着しなかったウェルズの方でした。
ウェルズが作り、ハーストが妨害した映画「市民ケーン」は、今では、映画史上最高傑作のひとつとして高く評価されています。
~ ~ ~ ~ ~
エゴをコントロールし、目的を成し遂げた事例
次にエゴに打ち勝ち、名誉を勝ち取ったのみでなく、社会をも変えた人物を紹介しましょう。
ジャッキー・ロビンソン(Jackie Robinson,1919 – 1972)は、アメリカで初の黒人メジャーリーガーになった野球選手です。
ロビンソンは、10代の頃、人種差別的な権威者に対して苛立ちを抱いていました。そのまっすぐな性格のため、友人へのアンフェアな警察の対応に抗議し、逮捕されたこともあります。
ロビンソンは、学業、運動ともに抜群でしたが、当時、黒人が仕事に就くのに学問は役に立たず、まだスポーツ選手として活躍できる場所は限られており、軍隊に入ったのち、1945年からニグロリーグでプレーしました。
ニグロリーグで好成績を収めた彼を、メジャーリーグチームのブルックリン・ドジャース監督でありオーナーであったブランチ・リッキー (Branch Rickey, 1881 – 1965)がスカウトします。
しかし、問題は、それまで誰一人として黒人でメジャーリーグでプレーしたことがなかったことです。黒人はあらゆる面で差別されていました。
スカウトの際、リッキーはロビンソンに尋ねます。
「君は様々な妨害や嫌がらせ、不公平な対応を受けるだろう。それでも決してやり返さない覚悟があるか?」
リッキーは、彼が遭遇するであろう様々な不遇をすでに予測していました。それは、遠征先のホテルの受付係から部屋を提供することを拒否されたり、レストランのウエイターから無礼な対応を受けたり、対戦チームから侮辱されたりといったことです。
ロビンソンは覚悟ができているとリッキー監督に告げ、ドジャースでプレーすることを決断します。そして、1947年ドジャースの一塁手として先発出場し、1880年代から黒人選手をニグロリーグに追いやってきたメジャーリーグにおける初の黒人選手になったのです。
しかし、入団後、ロビンソンは様々な冷遇を受けました。そもそもドジャースを除く全15球団がロビンソンがメジャーでプレイすることに反対していました。
フィリーズの監督は特にひどいものでした。ロビンソンが出場するなら対戦を拒否すると通告したり、プレー中も「ジャングルで待ってるぞ、ブラックボーイ!」「ニガー、ここはお前がいる場所じゃないぞ!」などと繰り返し、繰り返し、ロビンソンを野次り続けました。
相手選手に意図的にスパイクを向けてスライディングされてアキレス腱を痛めたこともあります。しかし、何があっても彼はリッキー監督との約束を守りました。様々な不当な扱いを受けながらプレーし続けた9年間で、一度も拳を振るったことはありません。それどころか記者からのリクエストに応じて、フィリーズ監督との写真撮影にさえも笑顔で応じました。
白人選手はひどいヤジを飛ばすファンに言い返すことがありましたが、ロビンソンにはその自由はありませんでした。
もし、一度でもやり返したならば、彼自身のキャリアを終えるだけでなく、彼に続く若く有望な数多くの黒人選手の門も閉ざすことになることを知っていたからです。彼は彼自身の人生を越えた大きな目的を担っていました。
ロビンソンは、誰もが罠に陥れようとするのを覚悟していなければなりませんでした。挑発に乗るのを避けるために、自らのエゴから常に自分自身を離しておかなければなりませんでした。
ドジャースでプレーを始めたとき、彼は28才でした。もちろん、その年齢でいかなる時も衝動を抑えるのは容易ではありません。しかし、彼はすべてを受け入れたのです。
彼は、最優秀新人賞を受賞し、1949年にはMVPにも選ばれます。しかし、彼はどんなに活躍し、自信をつけ、有名になろうとも、決してそれを台無しにするような行動を取りませんでした。
彼が特に人徳に優れていたからではありません。彼は、私たちが感じるような怒りやフラストレーションを常に抱えていました。しかし、大きく強い目的意識が、彼をエゴにかられた行動に移すことを抑えたのです。
~ ~ ~ ~ ~
今も昔も変わらない人間のエゴ
この2つの物語は過去の出来事ではありません。
今の時代、私たちが今いる社会にも同様に当てはまります。大きな目的のため、意義あることのために何かを成し遂げようとすると、様々な人たちから様々な批判や抵抗に遭います。
黒人選手のロビンソンが受けた冷遇ほどではないにしても、「やっても時間のむだ」とか「バカじゃないの」などと冷やかな目や批判の声を浴びせられるだけでなく、あからさまな妨害を受けることもあります。
あなたはそれにやり返したくなります。同じような汚い言葉を使って応戦したくなります。しかし、感情的になって反応してはいけません。逆に何もしないのです。ただただ、温かく受け流すのです。
どんなことであれ、長く社会に定着したシステムや考え方を変えるのは容易ではありません。
自分自身を確立し、自分自身がその変化を実践しない限り、変化を社会に浸透させることはできません。
世界に変わってほしいのであれば、まず初めに変わった後の世界を自らが体現するのです。自分が真っ先に行動すると決断した時点で、多くのことが簡単に思えるようになります。自分が実行に移せばいいだけだからです。一方で、多くのことが難しくもなります。なぜなら、自分がやっていることに矛盾があり、妥協のように感じられてしまうことがあるからです。
最も大きな成果を上げた人たちは、「自分を低く保つ」人たち、つまり、決して興奮したり自制心を失ったりせず、常に冷静で、落ち着いていて、忍耐強く、礼儀正しい人たちだ。
~ ブッカー・T・ワシントンI have observed that those who have accomplished the greatest results are those who “keep under the body”; are those who never grow excited or lose self-control, but are always calm, self- possessed, patient, and polite.
~ Booker T. Washington
~ ~ ~ ~ ~
他人のエゴとうまく付き合う
私たちは、エゴに駆られて自分本位な行動を取ったり、不誠実な対応をする人たちに囲まれて生活しています。
エゴに駆られて、会社を私物化し、大きな損害を与える経営者がいます。エゴを守るために、あらゆる挑戦を避け、ゆっくりと会社を沈没させていく経営者がいます。小さなエゴを傷つけないように、自己防御に必死になり、自分を成長させることができない人たちがいます。
そのような人たちのエゴを逆なでしてはいけません。なぜなら、あなたが望む結果と反対の結果をもたらすからです。その人たちを改善できないだけでなく、むしろ自分の人生を悪化させていくからです。逆境や不遇で、私たちは誰かを責めたり、憎んだりしがちです。しかし、他人を責めることで自分の人生を蝕んでしまう無限のループに入り込んでいきます。
他人に自分の人生を崩壊させる必要はありません。私たちはそれを防ぐことができます。
~ ~ ~ ~ ~
自分自身のエゴと向き合う
エゴは放っておくと、静かに確実に私たちを蝕んでいきます。それを避けるために、私たちは定期的に自分自身と向き合わなければなりません。
筆者ライアン・ホリデイの友人であり、哲学者で、武道家でもあるダニエレ・ボレッリ(Danicle Bolelli, 1974 -)はこのような比喩で表現しています。
「トレーニングとは、床掃除のようなものだ。一度掃除したからといって、永遠にきれいであるわけではない。むしろ毎日少しづつ埃が積み上がっていく。そのため、私たちは毎日掃除しなければならない。」
エゴも同じです。放っておくと、埃や塵がどんなに大きな害をもたらすことか、そして、掃除してもどんなに早く積み上がるかに驚くでしょう。
かつて、私たちの社会は、定期的に自分と向き合い見直す機会を提供していました。
キリスト教では日曜日に礼拝に行きます。イスラム教では金曜日が安息日、ユダヤ教では土曜日です。熱心な仏教国のタイやミャンマーでも、定期的な参拝を欠かしません。
それらは、祈りの時間であるだけではなく、定期的に自分と向き合う時間も提供していたのではないかと私は思っています。
本来、クリスチャンにとってプライドは罪です。なぜならプライドは「嘘」だからです。
エゴは私たちに嘘をつかせます。本当の自分よりも自分を大きく見せようとします。自分を良く印象付けようとする人は、真に印象深い人とは全く異なります。プライドは傲慢や欲望へと発展し、自己欺瞞と幻想を引き起こし、現実の世界と自分の間に高い壁を築き、他人との良好で健全な関係を妨げます。
私たちが自分自身をより知る機会を定期的に持たない限り、方位磁石が常に私たちを北に導くように、エゴは確実に私たちを失敗へと導いていきます。
私は特定の宗教を信仰しているわけではありませんが、かつて宗教が私たちにもたらしていたエッセンスを取り戻す必要があるのではないかと感じています。
私たちは、忙しさに駆られています。いいえ、忙しくする必要もないのに、無理やり時間を埋めて忙しいふりをして、「時間がない」と自分に言い訳をして、自分と向き合う時間を失っています。貴重な隙間時間でさえ、自分自身ではなく、スマホと向き合っています。
黒人選手のロビンソンが経験したような大きな試練に向き合うことはないでしょうが、それでもなお、日々他人から受ける数多くのナンセンスと向き合っていかなければなりません。
誰か何をけしかけてこようが、自分自身で自らの質を下げてはいけません。自分で自分の身を守らなければなりません。
第1の原則は、自分自身を騙してはいけないということ、そして自分自身が一番騙されやすい人間だということだ。
~ リチャード・ファインマンThe first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool.
~ Richard Feynman
~ ~ ~ ~ ~
さいごに
エゴは人間の本性であるため、まったくエゴがない人は存在しません。エゴは常に私たちに付きまといます。どこに行っても付いてきます。
もし、あなたが次のように考えているのであれば、あなたもエゴにやられ始めています。自分と一度向き合ってみてください。エゴの存在に気づけば、それを批判的に見ることができます。
- 私は重要なポジションにいるから、重要な人間だ
- 私は事業で成功したから、すべての秘訣を知っている
- 私より低いポジションにいる人たちは、自分に尽くす必要がある
- 私は起業したから素晴らしい
- 私は社長になったから、会社で一番偉く偉大だ
- 私は偉くなったから、人を利用してもよい
- 私は一流会社に就職したから、二流三流の会社に勤めている人たちより人間的に優れている
- 私は出世したから人生に成功したんだ
- 私は投資で成功して金持ちになったから、人生の勝利者だ
- 私の方が稼いでいてお金を持っているから、人間としての価値も高い
- 自分は成績優秀だから、人間としても優れている
- 私は正しいから変わる必要がない
- 私は静かでおとなしいからエゴがない
私たちに必要なのは、カチカチに固まったエゴやプライドではなく、現実と向き合い、自分を知り、自分を変化させたり、環境に適応することができる柔軟さであり、賢慮さ、規律、好奇心、学ぶ力、自ら動き挑戦する力、誠実さ、バランス、感謝の気持ちです。成功したと思うほどに、私たちは以前よりも増して謙虚にならなければなりません。
私たちは誰もがそれぞれの才能とポテンシャルを持っています。しかし、エゴはそれらを利用するのを妨げるだけでなく、ダメにしていくのです。
傲慢な人は常に物事や他人を見下す。そして、もちろん、見下している限り、自分より上にあるものを見ることはできない。
~ C.S.ルイスA proud man is always looking down on things and people; and, of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you.
~ C.S.Lewis